-

日本製 薄板(うすいた)角 蛤端(はまぐりば) 杉木地(花台)
¥8,700
日本製の角の薄板(うすいた)の ご紹介です。 薄板とは、花入の下に敷く薄い板で、 床の間などに花入を飾る時に花台のような 役割をします。 蛤端(はまぐりば)とは、この薄板の四辺の 端の部分が、貝の蛤の合口のような尖った 形に仕上げられているものをいいます。 この薄板は「真・行・草」の内、日常喫茶の 「草」の部類に入ります。 「真」は仏様や貴人への供茶などの献茶に 類する正式な茶事で「行」は「真」と 「草」の中間になります。 この薄板に合わせる花入も「草」の花入を セレクトして頂くとより引き立つと 思われます。 「草」の花入とは、無釉陶や自然釉陶などに なります。 伊賀焼や信楽焼、備前焼、丹波焼などが それに当たります。 また、竹の花入れを置くこともあります。 こうした茶道の約束事はその理由があるので ルールに沿った方が、花や道具がより 引き立つと思われます。 自然の杉ですので、木目がそれぞれ異なって おり、それが個性となっています。 41㎝ × 28.5㎝ × 厚さ0.5㎝ 木製 杉材 Made in Japan – Thin Rectangular “Hamaguriba” Cedar Wood Flower Stand (Usuita) This is a Japanese-made usuita (thin wooden board) with a rectangular shape and hamaguriba (clam-edged) design. An usuita is a thin wooden board placed beneath a flower vase (hanaire), serving as a kind of stand when displaying the vase in a tokonoma (alcove). The term hamaguriba refers to the distinctive finish on all four edges, shaped to resemble the sharp, matched lips of a clam shell. This usuita belongs to the “Sō” (informal) category within the tea ceremony classifications of “Shin, Gyō, Sō” — formal, semi-formal, and informal styles used in daily tea gatherings. “Shin” is used for formal tea ceremonies, such as offerings to deities or noble guests, while “Gyō” lies between Shin and Sō. To harmonize with this usuita, it is recommended to select a flower vase that also belongs to the Sō category. Flower vases classified as Sō typically include unglazed or naturally glazed pottery, such as Iga ware, Shigaraki ware, Bizen ware, or Tamba ware. Bamboo vases may also be used for this style. In the tea ceremony, such conventions exist for good reason — following them helps to enhance the natural beauty of both the flowers and the utensils. As this usuita is made from natural Japanese cedar, the wood grain varies from piece to piece, giving each one its own unique character. Dimensions: 41 cm × 28.5 cm × Thickness 0.5 cm Material: Japanese Cedar Wood 日本製 薄板角形 蛤口边 杉木底座(花台) 这是一款日本制的方形薄板花台的介绍。 所谓“薄板”,是指摆放在花器下方的一块薄木板, 在于床间或茶室中陈设花器时,起到类似花台的作用。 “蛤口边”指的是薄板四周的边缘部分, 其形状打磨成如蛤蜊壳合口般的尖细弧形, 这一特征正是其名称的由来。 这款薄板属于茶道中“真・行・草”之分的“草”之类, 即用于日常品茶的随意、质朴风格。 “真”用于供奉佛前或贵人等正式茶事, “行”则介于“真”与“草”之间。 若将此薄板与“草”风格的花器搭配使用, 更能相互衬托出自然之美。 所谓“草”的花器, 多为无釉陶或自然釉陶器, 如伊贺烧、信乐烧、备前烧、丹波烧等皆属此类。 有时也会摆放竹制花器。 这些茶道的规矩皆有其深意, 遵循其法则,更能使花与道具相得益彰。 由于使用天然杉木制作, 每块木纹皆不相同,这正是其独特之处。 尺寸:41厘米 × 28.5厘米 × 厚0.5厘米 材质:杉木(木制)
-

日本製 薄板(うすいた)上 角 蛤端(はまぐりば) 焼杉(花台)
¥13,300
日本製の角の杉材で作られた薄板 (うすいた)のご紹介です。 こちらは焼杉となっており、杉の表面と 裏面を軽く焼いて、うっすらと焦げ目が 付けられています。 表面を焼くことで、汚れや変色などを防ぐ 意味と、古い茶室などの侘びた雰囲気に 合わせるために、焼杉の薄板を使う場合が あります。 薄く丁寧に焼いてあるので、木目が よく見えて、風情のある雰囲気に 仕上がっています。 花入自体や飾る場所の雰囲気によっても、 使う薄板を変える場合があります。 薄板とは、花入の下に敷く薄い板で、 床の間などに花入を飾る時に花台のような 役割をします。 蛤端(はまぐりば)とは、薄板の四辺の端の 部分が、貝の蛤の合口のような尖った形に 仕上げられているものをいいます。 この薄板は「真・行・草」の内、日常喫茶の 「草」の部類に入ります。 「真」は仏様や貴人への供茶などの献茶に 類する正式な茶事で「行」は「真」と「草」 の中間になります。 この薄板に合わせる花入も「草」の花入を セレクトして頂くとより引き立つと 思われます。 「草」の花入とは、無釉陶や自然釉陶などに なります。 伊賀焼や信楽焼、備前焼、丹波焼などが それに当てはまります。 また、竹の花入れを置くこともあります。 こうした茶道の約束事は、必ずその理由が あるのでルールに沿った方が、花や道具が より引き立つと思われます。 自然の杉ですので、木目がそれぞれ異なって おり、それが個性となっています。 41㎝ × 29㎝ × 厚さ0.5㎝ 木製 杉材 Made in Japan – Thin Rectangular Board with “Clam Shell” Edges – Charred Cedar (Flower Stand) This is an introduction to a thin rectangular board made from Japanese cedar. This board is crafted from charred cedar, where both the front and back surfaces have been lightly scorched, leaving a faint charred finish. Charring the surface serves two purposes: it helps protect the board from dirt and discoloration, and it also complements the rustic aesthetic of traditional tea rooms, which often embrace a wabi-sabi atmosphere. Because it is gently and thinly charred, the wood grain remains clearly visible, creating an elegant and atmospheric finish. Depending on the type of flower container and the overall setting, different boards may be selected for display. A “usu-ita” (thin board) is a slender piece of wood placed beneath a flower container, serving a role similar to that of a flower stand when arranging flowers in an alcove (tokonoma) or similar space. The term “hamaguriba” refers to the shape of the board’s four edges, which are carved to resemble the sharp joint of a clam shell. This particular board falls under the “sō” (informal) category within the three traditional classifications of tea utensils: shin (formal), gyō (semi-formal), and sō (informal), used for everyday tea gatherings. “Shin” is used for formal tea ceremonies such as offerings to Buddha or honored guests, while “gyō” is a middle ground between formal and informal. To harmonize with this sō-style board, it is ideal to pair it with a flower container of the same category. “Sō”-style flower containers include unglazed ceramics or those with natural ash glazes, such as Iga ware, Shigaraki ware, Bizen ware, and Tamba ware. Bamboo flower containers may also be used. In tea ceremony, such conventions always have meaningful reasoning behind them. Following these rules helps to better highlight the beauty of both the flowers and the utensils. As this product is made from natural cedar, each piece has a unique wood grain, which adds to its individual character. Dimensions: 41 cm × 29 cm × 0.5 cm thick Material: Japanese Cedar Wood (Sugi) Made in Japan 日本製 薄板方形蛤蜊口燒杉(花台) 這是一款由日本製的方形杉木製成的薄板(うすいた)。 此款為燒杉工藝,表面與背面經過輕微炙燒,呈現出淡淡的焦痕。 通過燒製表面,不僅可以防止污漬與變色,也能與古老茶室等具有寂靜風情的空間相呼應,因此有時會使用燒杉薄板。 燒製得十分細緻輕薄,木紋清晰可見,整體呈現出風雅的氣氛。 根據花器本身及擺放地點的氛圍不同,所使用的薄板也可能有所變化。 「薄板」是指放置於花器下方的一塊薄木板,在在如床之間等處擺放花器時,起到花台的作用。 所謂「蛤蜊口」,是指薄板四邊的邊緣部分,被打磨成如蛤蜊殼合口一般銳利的形狀。 此薄板屬於「真・行・草」中的「草」類,用於日常的簡便茶會。 「真」是指供奉佛像或貴人時的正式茶事,「行」則是介於「真」與「草」之間的中庸形式。 若能搭配「草」類型的花器,更能襯托此薄板的風格。 「草」類的花器,通常為無釉陶器或自然釉陶器。 如伊賀燒、信樂燒、備前燒、丹波燒等,皆屬於此類。 有時也會使用竹製花器。 這些茶道中的規範皆有其道理,遵循規矩,反而能更好地襯托花與器物的美感。 由於是天然杉木製成,每塊木板的木紋皆不相同,這也成為其獨特的個性。 尺寸:41公分 × 29公分 × 厚度0.5公分 材質:杉木(木製)
-

越前塗 木製 薄板(花台) 角 蛤端(はまぐりば)黒 掻き合せ
¥7,260
越前塗から木製の薄板(花台)の角型の ご紹介です。 薄板とは、花入の下に敷く薄い板で、 床の間などに花入を飾る時に花台のような 役割をします。 蛤端(はまぐりば)とは、この薄板の端の 部分が、貝の蛤の合口のような尖った形に 仕上げられているものをいいます。 この薄板は「真・行・草」の「行」の部類に 入ります。 「真」は仏様や貴人への供茶などの献茶に 類する正式な茶事で、「行」は「真」と 「草」の中間になります。 この薄板に合わせる花入も「行」の花入を セレクトして頂くとより引き立つと 思われます。 茶道では、施釉の国焼や木や竹の花入れを 使うことになっていますが絶対というわけ ではなく、その時々の周りの状況や使う 花入れの雰囲気や風合いによって、最適な 薄板をセレクトして頂ければOKです。 置き物や飾り物などを置いて頂いてもよく、 自由な使い方が出来ます。 この角型が最もよく使われます。 本来は真塗りか木地のものですが、 掻き合わせ仕上げになっており塗っては ありますが、木目が見える塗りが 施されています。 41㎝ × 28.8㎝ × 厚さ 0.6㎝ 木製 掻き合わせ塗 Echizen Lacquerware Wooden Thin Board (Flower Stand) Square, Hamaguriba Black, Kaki-awase Finish We are pleased to introduce this square-shaped thin board (flower stand) made from wood, in the Echizen lacquerware style. A thin board refers to a thin wooden board placed under a flower vase, serving a role similar to a flower stand when displaying flowers in a tokonoma (alcove). The term hamaguriba refers to the sharp, clam-shell-like shape at the edges of the thin board, resembling the joint of a clam shell. This thin board belongs to the gyou category in the "Shin, Gyou, Sou" classification system. Shin refers to the formal tea ceremonies, such as offering tea to Buddha or dignitaries. Sou refers to informal or casual tea settings. Gyou falls between Shin and Sou, representing a middle ground. It is recommended to pair this thin board with a flower vase from the gyou category to further enhance the display. In the tea ceremony, lacquered ceramics, wooden, or bamboo vases are typically used, but there are no strict rules. The choice of thin board can vary depending on the surrounding context and the atmosphere or texture of the flower vase being used. This piece can also be used to display objects or decorative items, offering versatile usage. The square shape is the most commonly used form. While it is traditionally either finished in a solid lacquer or left in its natural wood state, this piece is finished with a kaki-awase technique, where the wood grain is still visible through the lacquer coating. Dimensions: 41 cm x 28.8 cm x Thickness: 0.6 cm Material: Wood, Kaki-awase lacquer finish 越前漆器 木制 薄板(花台)角形 蛤端(哈玛利巴)黑色 刮合漆 这是一款来自越前漆器的木制薄板(花台)角形的介绍。 薄板是指放置花器下方的薄板,当将花器陈设在床间等地方时,起到类似花台的作用。 蛤端(哈玛利巴)指的是薄板边缘部分呈现出像蛤蜊壳合口那样尖锐的形状。 这款薄板属于“真・行・草”中的“行”类。 “真”类适用于佛像或贵人供茶等正式茶事,而“行”则介于“真”和“草”之间。 如果选择适合“行”类别的花器搭配这款薄板,会更能突出其美感。 在茶道中,通常使用施釉的国烧或木竹材质的花器,但并不是绝对的要求。根据当时的环境、花器的气氛与风格,可以选择最适合的薄板。 除了用于花器外,也可以放置摆件或装饰品,具有很大的自由使用空间。 这款角形薄板是最常用的款式。 本来是纯漆或木质的,但采用了刮合漆工艺,虽然涂漆,但木纹依然可见,呈现出美丽的木质效果。 规格: 41cm × 28.8cm × 厚度 0.6cm 木制 刮合漆
-

越前塗 木製 薄板(花台) 角 蛤端(はまぐりば)黒真塗 本うるし 手塗り
¥11,330
SOLD OUT
越前塗から木製の薄板(花台)の角型のご紹介です。 薄板とは、花入の下に敷く薄い板で、床の間などに 花入を飾る時に花台のような役割をします。 蛤端(はまぐりば)とは、この薄板の端の部分が、 貝の蛤の合口のような尖った形に仕上げられているものを いいます。 この薄板は「真・行・草」の「行」の部類に入ります。 「真」は仏様や貴人への供茶などの献茶に類する正式な茶事で 「行」は「真」と「草」の中間になります。 この薄板に合わせる花入も「行」の花入をセレクトして頂くと より引き立つと思われます。 茶道では、施釉の国焼や木や竹の花入れを使うことに なっていますが絶対というわけではなく、その時々の周りの 状況や使う花入れの雰囲気や風合いによって、最適な薄板を セレクトして頂ければOKです。 置き物や飾り物などを置いて頂いてもよく、自由な使い方が 出来ます。 この角型が最もよく使われ、茶道では本来は真塗りか 木地のものが多く、この薄板は本うるしを使って 手塗りされており、高級な仕上げになっています。 41㎝ × 28.8㎝ × 厚さ 1㎝ 木製 本うるし 手塗り
-

越前塗 木製 薄板(花台) 丸蛤端(はまぐりば) 黒 手塗り 本うるし
¥10,780
越前塗から木製の薄板(花台)の丸型のご紹介です。 薄板とは、花入の下に敷く薄い板で、床の間などに花入を飾る時に 花台のような役割をします。 蛤端(はまぐりば)とは、この薄板の端の部分が、貝の蛤の合口のような 尖った形に仕上げられているものをいいます。 この薄板は「真・行・草」の「行」の部類に入ります。 「真」は仏様や貴人への供茶などの献茶に類する正式な茶事で 「行」は「真」と「草」の中間になります。 この薄板に合わせる花入も「行」の花入をセレクトして頂くと より引き立つと思われます。 茶道では、施釉の国焼や木や竹の花入れを使うことになっていますが 絶対というわけではなく、その時々の周りの状況や使う花入れの 雰囲気や風合いによって、最適な薄板をセレクトして頂ければOKです。 置き物や飾り物などを置いて頂いてもよく、自由な使い方が出来ます。 角では大き過ぎたり、角型の花入れには丸の花台が合う場合がございます。 シンプルなので、永くお使い頂ける逸品です。 径 31.3㎝ 高さ 1㎝ 木製 本うるし 手塗り Echizen Lacquer – Wooden Thin Board (Flower Stand) – Round with Hamaguriba Edge – Black, Hand-Lacquered with Genuine Urushi Introducing a round wooden thin board (usuita) flower stand finished in Echizen lacquer. A usuita is a thin board placed beneath a flower vase, serving the role of a flower stand when displaying a vase in the alcove (tokonoma), for example. Hamaguriba refers to an edge finish in which the rim of the board is shaped to a pointed form resembling the joined lips of a clam (hamaguri). This thin board belongs to the category of Gyō within the “Shin–Gyō–Sō” ranking system. Shin represents the most formal level, such as tea ceremonies for offering tea to deities or esteemed guests, while Gyō is the middle level between Shin and Sō. Pairing this board with a flower vase classified as Gyō will enhance the overall harmony even further. In the tea ceremony, it is customary to use flower vases made of unglazed or glazed local ware (kuni-yaki), wood, or bamboo, but this is not an absolute rule. Depending on the surrounding environment, as well as the character and texture of the flower vase you are using, you may freely select the most suitable thin board. It can also be used as a stand for ornaments or decorative objects—there are many free and versatile applications. In situations where a square stand is too large, or when a square flower vase pairs best with a round stand, this type can be an ideal choice. With its simplicity, it is a refined piece that can be used for many years. Diameter: 31.3 cm Height: 1 cm Wood – Genuine Urushi Lacquer – Hand-Lacquered 越前涂 木制 薄板(花台) 圆形蛤端 黑色 手工涂 本漆 下面为您介绍来自越前涂的木制薄板(花台)圆形款。 所谓“薄板”,是指铺放在花入(花器)下方的一块薄板,在床之间等处陈设花入时,起到如花台般的装饰与衬托作用。 “蛤端”是指薄板的边缘部分被加工成如蛤蜊壳闭合处一般的尖形轮廓。 此薄板属于「真・行・草」中间的「行」的类别。 “真”用于供奉佛前或贵人等献茶之类的正式茶事,而“行”则处于“真”和“草”之间的等级。 搭配此薄板时,选择同样属于“行”类别的花入,将更能相互衬托、相得益彰。 茶道中通常会使用施釉的国烧花入,或木制、竹制的花入,但并非绝对固定,应根据当时的环境、所用花入的气氛与质感,选择最适合的薄板即可。 也可用于摆放其他置物或装饰品,可自由灵活运用。 当角形薄板过大或角形花入不易协调时,圆形花台可能会更加相称。 设计简洁大方,是一件可长期使用的逸品。 径 31.3 cm 高 1 cm 木制 本漆 手工涂
-

日本製 木製 丸香台(花台)桐一枚板 掻合せ 黒 上
¥17,500
SOLD OUT
日本製の木製・丸香台(花台)のご紹介です。 丸香台とは、本来茶道で使う花入れの下に敷く花台で 畳の床の間などに置いて使います。 丸香台は、竹や楽焼など「草」の格の花入れに用いるとする資料と 蛤端と同様に(施釉の国焼などに)用いるとする資料もあります。 これは、絶対にこうでないといけないということではなく、 その時々の周りの状況や、花入れの風合いによって、 よく合う方を選んで頂ければと思います。 ましてや、茶道にあまり関係のない方は、置き物や飾り物に使って頂いてもいいし 様々な花入れなどを飾って頂いても問題ございません。 一応は茶道の中でこのような決まり事があるということだけ知った上で より似合う方法で自由な使い方をして頂いた方がいいかもしれません。 この丸香台は(花台)は桐材の一枚板を使ってるので、大変軽く持った瞬間に 上質であることが、すぐ分かります。 木目がうっすらと見える掻合せは、塗りに比べて傷も目立ちにくく 気軽にお使い頂けます。 シンプル故に永くお使い頂ける花台です。 径 31.5㎝ 厚さ 1.5㎝ 木製 桐一枚板
-
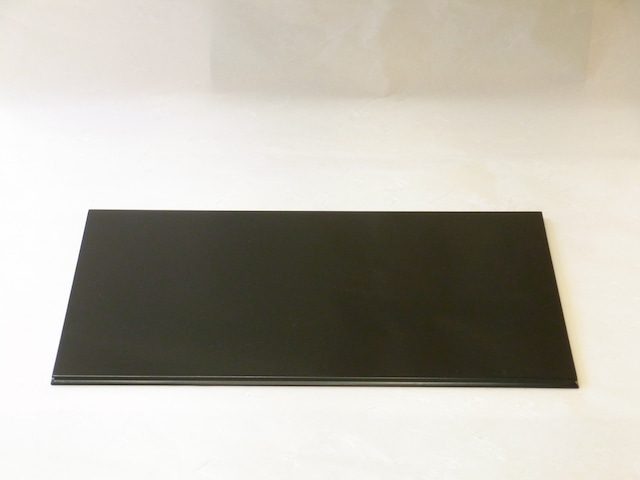
越前塗 薄板(花台) 矢筈(やはず)木製 本漆 手塗り
¥11,550
SOLD OUT
越前塗から、薄板の一種 矢筈板(やはずいた)のご紹介です。 矢筈板とは、茶道の席で花入れを床の間(畳床)に置く場合 薄板に載せることになっており、花台のような役割をします。 薄板には何種類かの板があり、この矢筈板は真の花入れを 置くことになっています。 真の花入れとは、胡銅・青磁・染付などで、最も格の高いものとなります。 この矢筈板は桧に真塗りされていて、木口 板の縁が矢の羽のように 切り込まれているので、矢筈と呼ばれています。 端の広い方を上にして用いることが約束となっています。 大きさも決まっています。 この矢筈板は手塗りされており、上ものとなっています。 43㎝ × 28㎝ × 1㎝ 木製 本漆 手塗り
